「適応障害」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
適応障害は急性ストレス障害(ASD)、心的外傷後ストレス障害(PTSD)と同様に、「ストレス性障害」というカテゴリーのなかに分類されます。
ストレス性障害とは、ストレスを受けたときに発症するさまざまな障害・病状の総称です。
そして適応障害は、「特定のストレスにうまく適応できなくなり、心理的負荷が強くなってしまうことで症状が出現する」障害を指します。しかし、これだけだとざっくりしすぎていてイメージが湧きにくいかもしれません。
適応障害は、「うつ病の手前」の段階とも言われます。
ストレスは適切に対応することで、乗り越えることが可能です。つまりストレスをうまく乗り越えられない状況になっているとき、適応障害となります。ストレスを乗り越えられない状態というのは心理的な負担がとても強くなっている段階です。
つまり、症状が出ている時点で「これ以上は心が危ない」とシグナルを発しているのです。
その時点で何らかの手立てを打たないと、うつ病に移行し回復に非常に時間がかかる状態になることがあります。
また、後述しますがストレスが長期間かかり続けることでうつ病だけでなくさまざまな疾患を引き起こす原因にもなりますし、命を脅かすことも珍しくありません。
人間がストレスに敏感であるのは、脅威が来ていることを正しく認識して、対処することが健康に生きていくために必要であるからです。
しかし個人の特性や、ストレスの大きさによってうまく対処できたり、できなかったりするのもまた事実です。
うまくストレスに対処できないとき、心にストレスがそのまま負荷としてかかってくることになり、「適応障害」という形で表面化することになります。
今回は、適応障害とはどのような障害なのか?近年とりあげられているビジネスパーソンのメンタルヘルスの問題も交えながら、症状や原因を具体的に解説していきます。
適応障害とは

適応障害を理解する時に、適応とは何かを簡単に押さえておきましょう。
適応とは、「生活する環境に対して適合できるよう、自分の行動や思考を変化させること」を指します。もちろん環境は変化するので、環境が変化したら自分の行動や思考も変化させる必要がある、ということですね。
環境の変化というのは例えば、
- 結婚・離婚・引っ越し・子どもの巣立ちなど家庭内環境の変化
- 就職・昇進・転職・部署移動など業務環境の変化
- 進学・転向など学業環境の変化
などが挙げられます。
ライフステージの変化に伴って、これらの環境も必ず変化していくという特徴があります。
たとえば進学した先で急に勉強が難しくなるかもしれません。
進学先が地元からかなり離れた場所で、見知った友人が誰もいない・・・といった環境に変わることもあるでしょう。
「勉強が難しい」とか、「見知った人がいなくて心細い」などといった環境は人によって程度に差はあれど、ストレスの原因そのものになります。
こういった場合、勉強時間を増やして“勉強ができない自分からできる自分に変える”とか、あるいは「勉強にはついていけないけど、まあ出来なくてもこのくらいの点数ならいいか」と折り合いをつける、というのが適応になります。あるいは別の趣味に打ち込み勉強のことはさほど気にならなくなる、なども適応的な反応として挙げられるでしょう。
新しい友人知人との関わりに重きを置くなど自分の中での“勉強の価値をいったん下げる”などして、行動や思考の変化でストレスに対処していくのも「適応」といえます。
適応とは、こういった形でありとあらゆる場面で発揮されるものです。本人が特段意識していないこともあり得るでしょう。
どの反応が正解というわけではなく、適応の形は多様です。
そして当然ながら、これらの反応が起こせない場合には「不適応」状態になり、さまざまな反応が現れます。
適応障害の症状
症状としては、
- 発汗・動悸・めまい・吐き気・頭痛などの身体症状
- 強い落ち込み・不安・怒り・焦りなど心理面での症状
- 暴飲暴食・問題行動(嗜癖行動)・違法行為など行動面での症状
などが挙げられます。
また、これらの症状はストレス因子に対する「ストレス反応」と呼ばれることもあります。
症状は上記のとおり色々ありますが、すべてストレスと戦っている状態であるからこそ起こる反応ということです。
前述の「進学先での勉強についていけない」例で言うと、
- 学校に行こうとすると行けなくなる
- 学校に行く前、強い頭痛がする
- 勉強しようとしても、動悸がして息苦しくなる
- 電車での通学中にめまいが酷くなり一駅ずつ降りる必要がある
といったことが挙げられます。
「勉強がうまくいかない」というストレス因子に対して、ストレス反応が起きている訳ですね。
特に学童期〜思春期などは問題行動となって表れやすく、その行動面に注目するあまり背景にあるストレス因子に気づきにくいことがあるので注意が必要です。
攻撃性が高まると、ストレス因子が消失していないあいだは家庭内暴力や非行、反社会的行動などが目立つようになります。
また、その攻撃性は他者だけでなく自分にも向けられることがあり、その場合は自傷行為など自分自身を傷つける行動につながることもあるでしょう。
嗜癖(しへき)行動
 嗜癖行動と言われる、ギャンブルへののめり込み・薬物の摂取がみられるケースもあります。嗜癖行動というのは依存症を指していて、「心身の健康や社会的な問題が出てきても、自分の意志でやめることが難しくなる状態」のことですね。
嗜癖行動と言われる、ギャンブルへののめり込み・薬物の摂取がみられるケースもあります。嗜癖行動というのは依存症を指していて、「心身の健康や社会的な問題が出てきても、自分の意志でやめることが難しくなる状態」のことですね。
健康を害しても、借金を繰り返しても、「もう二度とやらない」と思っていても繰り返し行動をやめられなくなってしまうのです。
ギャンブルや薬物といった対象は、脳内にドーパミンをはじめとした報酬系の物質を放出させます。脳の興奮を落ち着かせる作用をする脳内物質が放出されることもあります。
それらの報酬系物質の働きによって快楽や高揚感を得たり、イライラや興奮を鎮静させることでストレスからくる不快な感情を一時的に減らすことができるため、何度も繰り返しているうちにのめり込み、依存してしまいやすいといえるでしょう。
このほか、買い物依存やアルコールの過剰摂取・暴飲暴食なども嗜癖行動に当てはまります。
ただ、もちろんこれらの嗜癖行動は根本的な解決にはなりません。ストレスを紛らわせているだけだからです。ストレス因子が続く限り、快楽的な行動や衝動で軽減させ続けるしかありませんし、何より嗜癖行動そのものが引き起こす心身のダメージを考慮すると、得策ではないといえるでしょう。
適応障害の原因
適応障害・つまり不適応の状態は、ざっくりいうと「適応できる能力が低い」か「ストレス因子の影響が大きい」ことが原因になる場合が多いです。
適応できる能力が低い
適応できる能力が低いと、ありとあらゆる変化に対して適応できないのかというとそういう訳ではありません。
具体的にどういうことを表しているかというと、
- プレイヤーから管理職に昇進したが、管理業務に慣れず仕事が続けられない
- 進学校に進みテストの点数が下がったことが頭から離れず、学校に行けなくなる
- バイト先の人間関係に馴染めず、職場に向かうことができない
- 塾の先生が威圧的な態度で、塾に行けなくなる
- 結婚すると生活がガラリとかわり、体調を崩してしまった
といったようなものになります。
たまたま適応できないパターンも多く存在する
人によってはさして問題にならないような環境でも、個人によってはその環境に適応できる能力が低い場合がありますし、グループには適応できているのにある特定の人にだけ適応できない、ということも当然あり得ます。
もちろん、管理職に就いた人全員が不適応状態になるわけではありません。結婚についてもそうですね。しかし人によってはとても大きなストレス因子になり得るのです。
つまりストレスが客観的にみて大きなものでなくても、適応障害と診断される可能性は十分にあるということです。
誰しも「今から管理業務に慣れていけばいいだろう」とか「あまりうまく進まないが、最初はこんなものだ」「結婚したのなら生活が変わって当たり前」という考え方ができるとは限りません。
どんなに高度な業務をこなしてきた人でも、少し職務内容が変われば職務の難度に関わらず適応できなくなるリスクがありますし、結婚すれば生活スタイルが変わって当たり前と予測していても、実際に生活してみると心が思っている以上についていかない、といったことは往々にしてあるのです。
テストの点数に関しても、それまで将来の目標のために勉強が第一だと考えていたり、とにかく良い成績を取ることが重要だと考えている場合、「勉強についていけていない」という事実は非常に大きなストレスになります。
また、それぞれ「今まではうまくいっていた」のであれば、より落差は大きくなります。
急に価値観の転換が出来るわけではないので、仕事が生きがいであったとか、勉強で良い成績を取るのが誇りであったとかそういうケースでは特に変化についていけなくなるパターンが出てくることを理解しておきましょう。
「過剰適応」という不適応
もう一つ、過剰適応という言葉があります。「適応しすぎる」というと分かりにくいですが、「環境に適応しようとしすぎて、なりふり構わない努力をする」というと解釈しやすいでしょうか。
管理職に昇進した例で説明するならば、
- 評価を気にしすぎるあまり色んな人の意見を取り入れようとして、結局物事が整理できなくなる
- 管理職として早く評価をしてもらえるよう、一心不乱に(自身を顧みず)仕事に励む
- 部下に嫌われないように、極力意見を言わなくなる・他人に意見を毎回擦り合わせる
- 本当はプレイヤーで居続けたかった願望を、無理やり抑え込む
などが挙げられます。
当然ですが、管理職という業務自体がストレスになっている場合、「管理職として認められれば苦痛には感じないはずだ」という考えは間違ってはいませんよね。
しかし、ストレスが苦痛であるあまり成果を急いだり、とにかく仕事を頑張れば大丈夫とひたすら仕事に勤しむことが、必ずしもいい結果を生むとは限りません。
他者からの評価はコントロールできませんし、エネルギーの消耗だけが激しくなって、管理業務どころか雑務すらままならないほど疲弊してしまう可能性も高いです。
他者からの期待に応えることが原動力になっていると、いつの間にか自分自身のSOSを捉えることが出来なくなります。自分より他人を優先しやすい・他人からの評価が常に気になるといった過剰適応を起こしやすい人も要注意といえるでしょう。
ストレス因子の影響が大きい
 強いストレス環境により適応障害を引き起こすパターンです。
強いストレス環境により適応障害を引き起こすパターンです。
こちらは成果主義を中心とした仕事量の増加・効率重視の考えが個人にとっての大きな負担となることが多く、近年取りざたされている過重労働やハラスメントによる過労死・自死精神疾患の発症とも関連性が高いのが特徴です。
- 時間外労働が月100時間以上続く
- 成果を認めてもらえない環境にある
- 上司・家族から注意しかされない
- 強く叱責される出来事があった
- 事故や事件・災害に遭遇し、しばらく元の生活に戻れる目途が立たない
- 身近な人と死別した
こちらの場合は適応能力の高さに関わらず、「どんな人にでも不適応が起こり得る」ストレス因子であるといっても過言ではないでしょう。
また、どちらの要因においても共通しているのは、「置かれた環境のなかで、自分の存在価値を見出す過程での失敗やつまづき」であり、適応障害が心理社会的な障害であるといわれる所以でもあります。
有病率
人口のおよそ5%ほどの人が適応障害といわれます。
2017年時点で適応障害と診断された人は41,000人とされ、2008年の調査時からすると2.5倍の数に増えています。
性差
正確な割合は現時点では確認されていませんが、有病率は男性よりも女性が多いとされています。
適応障害の診断と予後
診断基準
DSM-5では、
1:はっきりとしたストレス要因がはじまって、3か月以内に症状が出現している
2:以下の2つのうちどちらかが当てはまる
2-1:そのストレス要因に不釣り合いな、強い苦痛を生じている
2-2:社会的・職業的に著しい障害をきたしている
3:ほかの精神疾患では説明できない症状である
4:正常な死別反応とは異なる症状である
5:ストレス因子が終息すると、6か月以内に症状が消失する
とされています。
また、死別はストレスが非常に強いものとされているため、症状が2か月程度出現するのは正常な死別反応と言われます。
しかし2か月を過ぎても症状が続く場合、適応障害と診断されます。
うつ病との鑑別の重要性
適応障害は強い落ち込みや不安などがみられることから、うつ病と似たような症状を呈します。
同じような症状なら治療法も一緒なのでは?と思われがちですが、適応障害とうつ病は治療方法やそれぞれの有効性が全く違います。そのため適応障害での症状なのか、うつ病での症状なのかはしっかり区別が必要です。
たとえば、
- ストレス要因がない環境(場所)だと症状がみられない(普通と変わらない)
- ストレス因子がなくなると、症状も比較的早く消失する
というのはうつ病にはない特徴です。
適応障害であれば、ストレス因子のない場面だと普通の心理状態になるため、旅行などを楽しんだり、趣味に勤しんだりすることもできます。
うつ病であれば環境や場所など関係なく一日中・毎日落ち込みがみられ無為の状態となり、ストレス因子に関係なく、数か月単位・年単位で症状は続いていくことが大半です。
また、元々興味があったことに対しても関心を示さなくなったり、旅行どころか外出すらままならなくなることも珍しくありません。
また、うつ病との鑑別が必要とはいっても、適応障害に対する適切なアプローチがなされないまま長引くと、うつ病に移行することがあるので早い段階で適切なサポートを受ける必要があります。
予後
前述の、「うつ病との鑑別」でも言及したとおり、本人がストレス因子から離れたり適切なサポート・治療を受けることができない場合、うつ病に移行することがあります。
また、適応障害そのものが予後に関わるわけではありませんが、不適応状態で起こる症状は「これ以上無理をすると危険である」という精神状態のバロメーターです。
しかし仕事の場合はストレス因子から離れることが困難であることが多く、過剰労働によって疲弊しきってしまっているケースもみられ、自分の置かれている状況の危険性を正しく認識していないことも多々あります。
その状態を放置していると、「過労死」を招いたり、自死に繋がる危険性があります。
過労死(karōshi)
仕事での長時間労働や強い心理負荷によって、脳梗塞・出血などの脳血管障害や心不全など内科的疾患・精神障害を発症し、死に至ることを「過労死」といいます。
過労死は今でこそ認知されていますが、1960年代までは仕事によるストレスが疾患の発症に繋がる、ということもあまり知られていませんでした。1978年に日本で初めてその用語が登場し、過労死で亡くなった方の遺族などの活動なども発端として日本の社会問題として注目されることになります。
また、世界にも「karōshi」という概念が広まり、海外でも過剰労働による過労死と認定される事例がみられるようになりました。
私たちは、生活しているなかでストレスに晒される機会がたくさんあります。しかし、仕事がストレスになって亡くなってしまう、ということはいまいち現実味がない話に感じる場合がほとんどだと思います。
むしろ、過労死に至るほどのストレスに晒されている人でさえ、自分の身に降りかかるとは思っていない場合もあるのです。実際に過労死診断を受けた人の6割は、医療機関にかかっていないとも言われます。
ストレスに適応できない状態になると、症状(ストレス反応)が起きます。そしてお伝えしたとおり、症状は「ストレスと戦ったり、逃げる準備を必死にしている証」です。
ストレスに負けないように全身を緊張状態にして戦闘態勢に入っているのと同じ、という解釈が正しいでしょう。
しかしストレス反応は、長く続けているとそのうち深刻な心身機能の異常を引き起こします。戦闘態勢であり続けるということは、それだけ過剰なエネルギーを使い続けるということです。そのうち記憶力が低下しはじめ、注意力が散漫になり、考えをまとめることが難しくなってきます。
そのレベルまで進んでしまうと脳萎縮や、脳細胞が死滅していくといった器質的な変化まで起こることも解明されています。
そのうち、自分の置かれている環境が自分にとって多大なストレスであることも、強いストレスを受けているという事実も分からなくなってしまったり、考えることを放棄する場合もあります。仕事を離れるという選択肢や、医療機関にかかってケアを受けるという手段をとらないままに、亡くなってしまうケースがあるということを忘れてはいけません。
適応障害の治療
基本的に通院治療がメインとなりますが、症状が非常に強く入院が必要と判断された場合は入院治療することもあります。
薬物療法や認知行動療法などがアプローチとして選択されるでしょう。
薬物療法
適応障害そのものを改善させるお薬は現在ありません。そのため、お薬を使って治療をする場合には対症療法(症状をやわらげるための)としての薬物療法や心理療法がメインになるでしょう。あくまで補助的な治療と考えるのがベストです。
抗うつ薬
脳内環境を整え、気分の落ち込みや意欲の低下を改善させるお薬です。適応障害が起因となってうつ病に移行している場合、また落ち込みがひどい場合は抗うつ薬の処方がなされることがあります。
ただ、適応障害で落ち込みやふさぎ込みがあったとしても、うつ病で起こる意欲の低下とは原因がまったく異なります。抗うつ薬の効果をしっかり判定しながら治療を進めないと、逆に回復に時間がかかることがあるかもしれません。
ですから、落ち込みの症状が見られたとしても状況によっては抗うつ薬が第一選択にならないこともあります。
医療機関で、正しく鑑別してもらうこと・また治療経過をしっかり追うことが重要になってきます。
抗不安薬
脳内の過活動を鎮め、不安や緊張状態を抑える働きを持つお薬です。
不安や焦り・興奮・恐怖心などが強い場合に使用することがあります。
睡眠導入剤
不眠などの症状が出ている場合にも、睡眠導入剤で生活リズムを整える手助けをする場合があります。不眠が出現している場合、考えがまとまりにくかったり不安やイライラを増強させたりする原因にもなるので、早めに対処する必要があります。
最も効果的であるのはストレス因子がなくなること
 適応障害の症状が速やかに改善するのは、やはりストレス因子そのものがなくなることです。
適応障害の症状が速やかに改善するのは、やはりストレス因子そのものがなくなることです。
そのため、環境に対して適応できるようになるよう支援する(ストレスであったものがストレスではなくなる)形と、環境が変えられるよう支援する(ストレス因子から離れる)、という形が適応障害の回復を考える上では基本となります。
明らかにストレス因子の影響が大きく、環境を変えるほかないといった場合も多いですから、そういった時はいったんストレス因子から離れるために配置転換をしてもらったり、休学・休職が望ましかったり、あるいは転校・転職が必要な場合もあるでしょう。
これらのパターンでも休職するには医師の診断書が必要です。休学は、病気を理由に休学する場合にはこちらも診断書を準備しなくてはなりません。症状が出ている間は苦痛が伴いますから、休職・休学が必要かどうかは医療機関と話し合いながら決めることが大事です。
休職の必要性
休むだけではストレスは無くならないのでは?というとその通りですが、ストレスから一時的にでも離れて自分の健常な生活・思考を取り戻すことで、これからの生活について改めて考え直すことができます。
対処方法を得るきっかけにもなるかもしれませんし、今までとは異なる環境に向かうための準備期間になることもあるでしょう。
どちらにしろ辛い症状に耐えて生活し続けていても、あまり良い結果は生まれません。休職や休学は、「仕切り直し」の時間と考えるとよいでしょう。
また、ストレス因子から離れるとはいっても状況によっては難しいこともあるため、乗り越えられるストレスかどうかを判断したうえで、認知行動療法を受けることも一つの手段です。
認知行動療法
適応障害における認知行動療法の役割は、
- 誤った思考パターンや認知のゆがみを修正し、健康的で現実的な認知に変えていく
- 問題解決や、環境に適応できる能力の獲得を図る
- 思考だけでなく、問題となる行動パターンを適切なものに修正する
- 否定的な自己評価から、自己肯定感を向上させる
- 適応障害の再発を防ぐためのスキルを獲得する
といった内容になります。
嗜癖行動にも有用
特に、適応障害の発症において嗜癖行動・ギャンブル依存や借金、アルコール依存など望ましくない反応がみられているときにも有用な手段です。
そもそも、どんなときにギャンブルや依存対象に走りたくなるのか?という所を分析したり、まずは短期間でも嗜癖行動から離れることを目標として、少しずつ嗜癖行動から離れていくようステップを踏んでいきます。
認知行動療法を集団で行うことも有効とされます。基本的に嗜癖行動は周りに理解者が得られることが少なく、本人が周りに隠している状況であることも珍しくありません。そのため、同じ境遇にいるメンバーと意見交換しながら目標に向かって進んでいくことが、当人の孤立を防ぎ、症状の改善に役立つのです。
「反芻思考」による不安を軽くする
- サークルの人が、自分にだけ当たりが強い気がする
- あの時自分の発言で友達が怒っていたのではないか
- 会議中のあの一言を言わなければよかった
こういった思考を何度も繰り返すことを反芻(はんすう)思考といいます。何度も繰り返し同じことをループして考えるという意味です。
しかし、ストレスが長期的に続いてくると、そのことが気になって頭から離れないとか、食事をしていてもベッドに入っていても同じことを繰り返し考えがちになることがありますよね。
考えれば考えるほど良い結果が出たり、ポジティブになれば良いですが、反芻思考で浮かんでくるものは大抵がネガティブな要素を含んでいて、何度考えてもどうしようもないことだったりします。しかし反芻思考が癖になってしまっている人が多数いるのも事実です。
この反芻思考の欠点は、ストレス因子が比較的弱いものでも長期間にわたって同じようなネガティブな思考を繰り返すことで、不安がどんどん強まるといったような状況に追い込まれるケースが存在することです。
認知行動療法では、これらの反芻思考から注意を切り替える役割も持っており、今対処すべきことに目を向けられるように促します。
反芻思考が起きるのは、一つのことにこだわりすぎていたり、物事に対する期待値が高いことが原因になったりもします。
そもそも抱えている不安は正しいものなのか(認知の偏りにより余計な不安が起きてはいないか)という観点でも、個人の認識を少しずつ適応的なものに改善できるよう、トレーニングを行うのも現状の改善の一つの手立てとして役立つでしょう。
まとめ
 適応障害は、ストレス因子から離れると普通に振舞うことができたり、活発に動くこともできることから、「怠け」と誤解を受けやすい障害でもあります。
適応障害は、ストレス因子から離れると普通に振舞うことができたり、活発に動くこともできることから、「怠け」と誤解を受けやすい障害でもあります。
しかし症状はとても苦痛なもので、円滑な社会生活を脅かします。
しかし、適応障害と診断される人の中には非常に実直でひたむきな方も多く、適応障害を引き起こしている本人自身が「もっと頑張らないと」「弱音を吐いていてはダメだ」と思い込みやすい障害ともいえます。
特に努力で乗り越えてきた、というタイプの方だと努力で乗り越える以外の選択肢がなかなか浮かばず、消耗しきってしまうパターンも少なからず存在するのです。
より自分を奮い立たせようとして無理をしてしまったり、精神的に追い詰められてしまったり、うつ病を発症したりするケースもとても多いです。
適応障害で起こっている症状は紹介したとおり様々なものがありますが、逆に考えれば、症状が出現することは心の負担が大きすぎるというサインでもあります。今の環境を見直すきっかけと捉えたほうがいいでしょう。症状の悪い側面だけに注目しがちですが、何がその症状を引き起こすトリガーになっているのかを早めに特定しておくことが何より重要です。
医療機関で相談してもらうことでも、何が要因になっているのか、その環境から離れることはできるのか、離れるためには何が必要なのか、ということが少しずつ見えてくるきっかけになるでしょう。
適応障害を乗り越えるには、周りの適切な支援も必要です。適応能力には、周りに適切にサポートを依頼できる力、というのも含まれています。まずは医療機関もサポート環境の一つとして活用してみる気持ちで、相談してみるのが良いでしょう。
監修
新橋メンタルクリニック
院長 狩野 彰宏
「メンタルケアで全ての人が今よりも生きやすく輝ける未来を目指して」
明るい未来を紡ぐために、当院は一心一意に皆様の心に寄り添ってまいります。
心のお悩みや困りごとがありましたら、どうぞ何なりとお問い合わせをくださいませ。
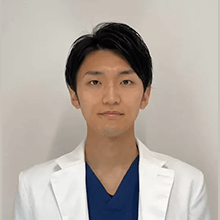
「メンタルケアで全ての人が今よりも生きやすく輝ける未来を目指して」
明るい未来を紡ぐために、当院は一心一意に皆様の心に寄り添ってまいります。
心のお悩みや困りごとがありましたら、どうぞ何なりとお問い合わせをくださいませ。







